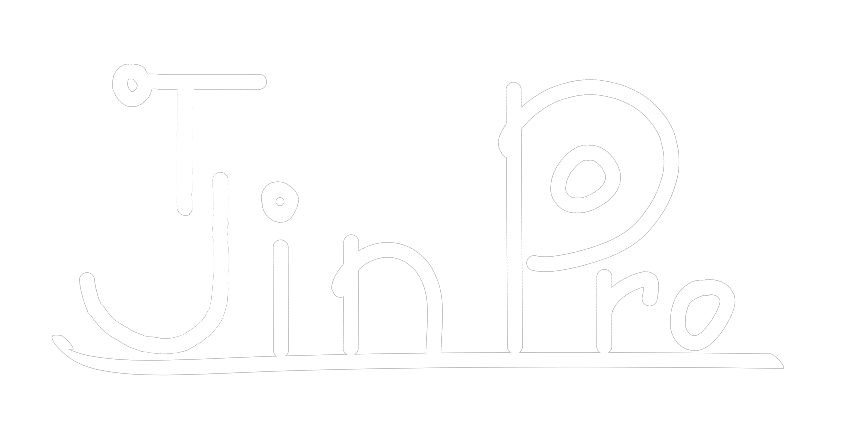みなさん、こんにちは。Jinです。いかがお過ごしでしょうか。
2025年が、やってきました。2018年に高専へ入学した私、Jinという一人のちっぽけな高専生の物語も、今7年間という長い夜を越えて、ようやく夜明けを迎えようとしています。
今日はそんな私の、7年に渡る高専生活のすべてをお話しようと思います。これは、以前書き記した高専半生の記憶 「高専での4年間と高専祭」と直接つながる、本当のお話です。
私がそんな7年間で見つけた、高専や世の中の理不尽で埋め尽くされた世界で生きていく術と、私流のそんな世界を変えていくための方法を、大公開します。またこの一つの記事でまとめてという形で大変恐縮ではございますが、そこに関わってくださいました多くの方々への感謝を申し上げます。
目次
ありふれた理不尽と、無力な私
仮初めの希望 – 2018
小中学校在学中、腐った世界で見つけた電子工作という輝かしい希望に没頭し、貧乏だった頃に粗悪な開発環境を構築し「ものづくり」の世界に参入した私にとって、学力という環境に囚われず与えられた平等な武器を使って得られる唯一の希望、それこそが「高専」という世界でした。
はんだ付けをさせてもらえる体験入学など、果たして当時の学校ではどれほどあったでしょうか。キラキラ輝くエンジニアを目指す先輩、その周りには沢山の仲間がいて、当時一人で無知な工作を追い求めていた私の理想の姿であったに違いありません。
しかし私が入学して目にした世界は、そんな光り輝くようなものではなく、もっと腐った世界でした。その苦悶を経験したときに、何度その継続の意志と断絶の決断に迫られたことでしょうか。
逃げれば楽だが、解決はしない。挑めば苦だが、解決には近づく。しかし自分の理想と社会の現実の狭間にある壁は遥かに高く、戦うべき相手は遥かに多く、守らなければならない者は遥かに脆く、共に戦う仲間は遥かに少ない…
私がどんな苦悶を体験したか、体験入学や学校説明会では決して語られることのない、高専とはどんな学校か、それを今ここで、私の高専七年の卒業記念にお話しようと思います。久しぶりの雑記(自伝)長編です。最後までお付き合いください。
2018年1月の推薦選抜、同年3月の一般選抜という二度の入学試験を経て私は、自分が抱いた理想の姿の、その千里の道の第一歩を踏み出しました。

電気技術研究会、柔道部、社会活動などたくさんの活動を初めた私は、高く掲げた理想を追い求め、この高専と世の中に、多くの希望を感じていたに違いありません。ここで何が学べるのか、楽しみで仕方ありませんでした。
残酷 – 2019
入部した柔道部では、仲間と呼べる仲間がいませんでした。同期は0人、先輩は私が初めて柔道部長となる2019年に全員引退し、同年に入って出来た後輩には、両立の不足が原因で次第に嫌われ、LINEをブロックされるような事態に陥ったこともありました。
電気技術研究会では、仲間がいました。当時の仲間には失礼ですが、まともに工作を出来たのは周りでは私くらいでした。また当時中学生の私が目を輝かせた高専祭や体験入学で、逆に電気科に人を呼び入れるため私は中学生を対象に、電気やものづくりの魅力を伝えなければいけませんでした。
その使命がどれだけ厳しく、骨が折れるかは想像に難くないでしょう。「電気科希望の星」と称され託された厳しい使命を高専に入って2年目のまだ幼い頃に任され、私には重い責任と期待、不安など様々な葛藤からくる重圧に耐えなければなりませんでした。
ただしその重圧は、本来好きなことであれば押し上げて突き進んでいけることでしょう。私は過去柔道部の顧問をされていた先生に問われました。「好きなことをしているはずなのに、どうしてそんなに辛くなるのだろうか」と。それが出来なかったのは、そこに付随したもっと過酷な現実に他ならないのです。

特に私が課題に思っていたのは、学生の意欲の低さでした。就職ができればそれでいいのか、楽に進学ができればそれでいいのか。人を幸せにするためにものを作るべきエンジニアを目指す我々が、自分のことばかりで本当にいいのか。
私は当時の担任に、卒業研究報告会へ連れて行ってもらいました。しかしその場で前の席に座る素晴らしいはずの先輩方に、「意識高い系」とこそこそ馬鹿にされて笑われていたことを鮮明に覚えています。
また工場見学で私は、卒業し就職した先輩に問いました。一体この学校で勉強したことがあなたの何に活かされているのか、と。そこにいた先輩3人のうち全員が、活かされていることは何もない、と答えたのは私に非常に衝撃を与えました。
私はこの過酷な現実を知りながら、あらゆる場で中学生には見かけ上の高専の姿だけを話してきました。「高専は素晴らしい学校である」と。そんな罪を重く受け止め、なんとかこれを変えなければと、当時の私は一人で必死になっていました。
しかしそんな苦しい想いに答えてくれる人間はおらず、掘れば見つかる過酷な世界がただそこにあるだけで、それを見つけてもどうすることも出来ない非力な人間がそれを見つけて、この残酷な世界にひれ伏すだけです。
この当時の心の拠り所といえば、奨学金支援を受けていたあしなが育英会の催す、「つどい」くらいだった記憶があります。「つどい」では、親を亡くした子どもたちが集まり、これまでの自分やこれからについて考えるプログラムで、私はそこでそんな世界を変えることを決意していました。

そしてそこには、同じように世界を変えようとしている有志がたくさんいたということを、あとになって気づきます。そしてそんな彼らは後に、かけがえのない仲間となっていきますが、そこに到達するまでには、数多くの困難がまだ残されていました。
荒野に咲いた花のような、そんな存在
停滞 – 2020
2020年、ただただ悔しく、恨めしい気持ちばかりが積もっていき、しかしなすすべもなく、重圧と地獄にもまれた私は、そのような心境で部活の積み重なるタスクに対処できず、留年という選択肢を取りました。
誰も何も変えることが出来ないお気持ちだけの大義を掲げ、ただ家族や友人、当時奨学金を借してくださっていたあしなが育英会にまで迷惑をかける愚かな選択をした私は、本当に世界を変えられる気でいたのです。
この年に襲ってきた新型コロナウイルスの影響によって、失われたものはたくさんあったでしょう。
特に自分の心の拠り所であった前述のあしなが育英会の催す「つどい」がなくなった衝撃は大きかったと覚えています。高専祭もオンラインとなり、より厳しいミッションに立ち向かっていかなければいけなくなりました。
クラブ活動が制約され何もすることができなくなった2020年は、過酷な現実を身に感じつつも目をそむけ遊び呆け、ただ悔しい気持ちを抱きながらも停滞することになりました。
挙句の果て、無責任に柔道部を後輩に一方的に押し付ける形で、引退することにしたのです。仕方なかったと言うことは簡単ですが、残された者の気持ちを推察しなかった私は、愚かの一言に尽きるでしょう。
しかしそんな残酷な世界にあらがう先輩たちの姿も当時目にしていました。「TalkCafe」と名付けられたLTイベントに参加し、登壇した私は、それを開催していた電気工学科の先輩にSNSで、「私たちはこれまで『きっかけづくり』の場を作ろうと思ってきた。独学が誰かのきっかけになれば、という登壇に感動した。」と褒められたことを覚えています。

-TalkCafe #4 オンラインにて
ただのイベントかもしれないが、それは前述のつどいだって同じです。小さなことが「きっかけ」となり大きく社会を変えていくという「きっかけづくり」の構図は、当時はじめから大きなことを起こしたいと奮起していた私に衝撃を与えたことでしょう。そしてその感動は、次の活動に繋がっていくこととなるのです。
前置きで書いた記事は、時間軸ではおおよそここまでの物語を綴ったものになります。高専祭ではしっかりと役目を果たしていましたが、あれも見かけ上のものであり、結局その裏では過酷な現実と戦い大敗し、目を背け逃げ続けていたのです。
そしてその後に待ち受ける、更に過酷な物語をこれからお話します。
反撃 – 2021
コロナが少し落ち着きを見せ、柔道部引退によって余裕が出来た2021年、「きっかけ作り」をみて変革起こそうと思った思い上がりは、まずは電気科での結束力を強めるための活動に足を踏み出します。私なりに、この世界を変えようと思い立った最初の行動でした。
まずこの年に電気技術研究会の部長となった私がはじめに着手したのは、「電気科Ring」と名付けたプロジェクトでした。新年度を機に電気技術研究会へ新しく入ったたくさんの同期とともに、電気科の中にある電気自動車を作るEVプロジェクトや、電気科の広報を担う広報プロジェクトなどを電気技術研究会とつなげる役割を果たそうというコンセプトを掲げていました。
これによって高専祭や体験入学などで電気工学科がより活発なものになると考えたのです。実際、電気科内で行うイベントも計画していました。しかし未熟で仲間すらまともに頼れない私には、コロナによって安定のしない世界で、これを遂行することが出来ませんでした。

電気科広報プロジェクトは事実上の崩壊、人手不足と活動制約の影響によってEVプロジェクトとの連携も取れず、また電気技術研究会が2021年のオンライン高専祭を境に、私ともう一人の同期を除く9割の部員が引退することで「過酷な現実」がより深刻化し、プロジェクトは消え去りました。
加えて、コロナで何も出来なかった夏休みに初めた、ウーバーイーツのバイトで起きた事故は更にこのときの私に追い打ちをかけます。最終的にほとんど当たり屋のような事件であったにもかかわらず、警察官に怒鳴られ、親に怒られ、加害者に脅迫される…というようなことを経験しました。
それまでの私は、私なりに必死に生きていたつもりでした。しかし夢だったものづくりの、より良い仲間と環境を欲しただけで、なぜこんな目に合うのか。理解できない現実と見つからない答えを探し求めていました。
非力な人間が現実に抗ったらこうなるんだと思い知らされた1年でありました。しかしこのとき立ち上がった選択は決して誤りではなく、そのどん底から一気に這い上がっていくフェーズがこれから来ることになります。
長い冬を越えた先には春がやってくる
足掻き – 2022
心境は悪くなるばかりで学校に行くのも億劫になり、世の中を憎み、ありとあらゆるものを恨み、消化できない大きな感情を抱き、しかし結局なすすべもなく、2回目の留年を迎えます。
そうだ、高専をやめよう。そう思いました。同じ立場にあれば、誰もがそう思うことと思います。
あしなが育英会から1年多く奨学金をもらい、親や家族に迷惑をかけ、散々期待を裏切ってきたくせに、結局何も出来ず、何も残せなかった。
だがいざ高卒認定(高専引退は最終学歴が中卒となるため)の書類を書いていると、どうしようもない後ろめたさが襲ってきます。そしてこの結末に、腹が立って仕方なくなりました。
また9割の人が引退した電気技術研究会へ新しく入った後輩の影響も大きく、結局続けるという選択肢を取ることになりました。

留年に加えて停学処分も受けていたその頃、もはや誰にも期待などされていなかったでしょう。後輩を育てものを作り、ただ今までどおり過酷な現実と戦いながら、電気工学科に人を呼び入れるための使命をこなすことになります。
私としても、もはや高専になんの希望も抱いてはいませんでしたが、犯した罪の分を償う必要があるのは事実なので、歩みを止めることは決して許されないことなんだと自分を言い聞かせていました。
私はこれまで、中学生にモノづくりの魅力を伝えるためのモノづくりをしてきたつもりでした。しかしそれはSNS上で「お遊び」と揶揄されます。どれだけいいと思えるものを作っても、どれだけ丁寧な言葉で説明しても、電気工学科の倍率は伸びなかった。
今やっていることすべて、自己満足のお遊びなのかなと、私は当時大きな罪を背負いながら、そんな葛藤とも戦っていたのです。その年にそんな心境を抱きながら製作・改良した展示品は5,6作品にものぼり、私の電気技術研究会での最盛期といえる時代となりました。

– 2022年 文化発表会(高専祭縮小版) 電気技術展にて
2022年の暮れ、3度目のオンライン高専祭。崩壊しかけていた高専祭実行委員会と真っ向から戦った記憶があります。「きっかけづくり」の場であるはずの高専祭において、その運営の粗末さに呆れて展示の辞退者を出し、高専祭の失敗がほぼ確実に目に見えていた時期がありました。
私は過去の先輩に恥じないよう、使えるどんな手段を講じても、これを全力で阻止しました。展示の辞退は無くせなかったものの、この足掻きは、少しは高専祭を成功に導いてくれたと思っています。そして神が私を試したかのように、この時のこの争いを境に、私の活動は日の目を帯びていくことになるのです。
変革 – 2023
コロナが、学校や部活動などの組織全体の体たらくをもたらしていたのは事実でした。今は卒業した先輩が抱いていた「きっかけづくり」はそこには見る影もありませんでしたが、コロナが出る前からそんな過酷な現実を幾度と目の当たりにしていたはずの私が、それしきのことでは決して私は抗うことをやめませんでした。
何かを変える信念は、執着でしょうか。その念を抱き続けることは、往生際が悪かっただけなのでしょうか。それは絶対に違うと今、胸を張って言うことができます。私たちはエンジニアを目指すべき学生であり、変えなければいけない現実があるなら、変えるためにモノを作るはずであり、そんな世の中をよくするために生まれた技術をもっておいて、行動を起こさず怠慢など、それこそ笑止千万です。
社会にはそれを必要とする世界は数多くあって、そこから目を背けるのは楽ですが、いつの時代も理想とする世界を、自分の手でつかみ取ろうとし、自分の足で歩み寄ろうとすることこそが変革を生み出してきました。目を逸らしてはいけない。現実は残酷で人間は無力だが、我々には技術がある。
そう志して徐々に変革を得るまで6年がかかりました。多くの犠牲を払いましたが、私は大切なことに気づき、小さな行動が大きな変革を生み出すことを知りました。そうして2023年に少しだけ、明るい未来を照らすことができたのです。
2023年の1月、奈良高専でTechRingを創設致しました。技術系団体が手を取り合って学科の壁を越え、高専の広報をするその姿は、私がまさに電気科で目指そうとした電気科Ringの拡大版でした。学科を超えて電気技術研究会に集まった後輩たちが、学科を超える大切さを気づかせてくれたのです。
その一環として同年4月、Maker Faire Kyoto2023に共同での初出展を成し遂げることができました。
TechRing創設に携わっていただいた学生、先生方には、深く御礼を申し上げます。

3月、共同代表として高専カンファレンスin福岡2023を開催しました。先輩方に教わった「きっかけづくり」を目指した成果物でありました。3年ぶりに開催されたこのLTイベントを機に、現在は数多くの高専カンファレンスが開催されています。また、8月にはTalkCafeを引き継いで「TechCafe」というLT会をTechRingで開催したりもしました。
当時高専カンファレンスin福岡にて、ご理解とご協力をくださいました協賛企業の方々には、改めて深く御礼を申し上げます。
また、高専カンファレンスやTechCafeにて運営を手伝っていただきました運営メンバーの皆様にも、改めて御礼を申し上げます。

7月頃から、高専生活で初めて「チャレンジプロジェクト」に参加するようになり、この年はTurtle Picoの開発と、コンテストの開催を「きっかけづくり」である草の根運動として行いました。
チャレンジプロジェクト「IoT アイディアものづくりキット」PJをご指導くださいました顧問の先生、コンテストに参加いただいた学生の皆様、アドバイザー企業の皆様に、深く御礼申し上げます。
さらに8月、4年ぶりに開催されることとなったあしなが育英会の「つどい」では、大学生スタッフである「リーダー」として支える立場でした。そこから私は「あしなが学生募金事務局」の存在を知り、事務局員となり、10月から募金に参加するようになります。
また、あしなが育英会がつどいで行っているような「グリーフケア」の存在を知り、親を亡くした子供たちを支える「ファシリテーター」となって、12月頃からグリーフケアに関わっていくようになりました。
高専生活として最後の高専祭は、3年ぶりにオンラインから対面に切り替わり、中でもノウハウをつないできた電気工学科展は盛況に終わることができました。

技術をもって仁を成す
そして社会運動へ – 2024
この年には電気技術研究会部長の役目を終え、逆にあしなが学生募金での立ち位置が大きくなり、2024年には事務局新設の「大阪中央ブロック」にてブロックマネージャーを拝命するようになります。全国で有志と議論したり、募金活動によって社会を良くしようと社会に働きかけるようになっていきました。
8月に行われたあしなが育英会の「つどい」では、前年よりも重要な役割である「シニアリーダー」として関わることになり、自分のTシャツにつどいのロゴを学校の起業家工房にある自動刺繍ミシンを使って縫い付けており、この場でも自分の技術が一部活かされています。

またその当時高専には、私が作った展示品を見て電気科に決めたという新入生が入ってくれて、電気工学科の雰囲気がガラッと変わります。技術に興味のないという高専生が減った現実を目の当たりにして、肩の荷が下りました。彼らのおかげもあり私は、お遊びといわれたものづくりで、しっかりとその役目を全うしたと、胸を張って語れるようになりました。
さらに、その年もチャレンジプロジェクトに参加し、「Life With 3D Printer」プロジェクトと題して、AIを用いて音声入力から自動でモデリングを行い印刷する3Dプリンターの開発に着手していました。
「Life With 3D Printer」PJをご指導くださいました顧問の先生、PJに参加いただいた学生の皆様、アドバイザー企業の皆様に、深く御礼申し上げます。
また夏ごろに、次の進学先である豊橋技術科学大学への編入が無事決まりました。そこではどんな物語が待ち受けているでしょうか。また、こちらのブログでご報告させていただけたらなと思います。
同時期から、自分のモノづくりを社会の役に立てるべく、株式会社マグチグループの物流DX推進を担う部署において、デバイス開発のインターンも始め、半年間お遊びじゃないモノづくりを実践することができました。非常にお世話になりました。これからそのインターンは後輩が引き継ぐ形で、継続されていきます。
そのように自分の力を試し、世に役立てることができる場を提供くださいましたマグチグループ株式会社の皆様には、深く御礼申し上げます。

その他、この年は2月に高専カンファレンスin浜松、3月にKariya Micro Maker Faire、7月にTechseeker Collection、9月に高専スペースキャンプ、10月にMIX Leap 大LT会、11月に関西オープンフォーラム、12月に Heroes Leagueなど、数多くのイベントを、毎月のように参加した年にもなりました。
そのすべてのイベントに携わり、開催いただいた皆様に深く御礼申し上げます。
あしなが育英会での活動でも、インターンでも、このいかに残酷な世界であっても、技術はどの場所でも光であることには変わりなく、そして自らでその光を操れる高専生になれれば、世界を変革することができると、私はこの年をもって証明しました。
ものづくりでできる社会運動とはどんなことでしょうか。私は「ものづくり」が主体になるものはほとんどないと感じています。世の中には数多くのボランティア活動が存在し、その都度いろんなスキルが必要になります。そこにものづくりが関われば、大きな進展をもたらすことになります。技術はあくまで手段であり、それを彩るのはその手段を講じる人に、大きく依存するのです。
夜明け – 2025
そして2025年が始まり、卒業論文を無事提出した私は、卒業を迎えました。
新たな活動のステージとして、2月にあしなが育英会の「つどい同窓会」を企画者として運営しました。そこでは2023年に携わった高専カンファレンスの経験が多く活かされました。アイスブレイクの企画一つと、班調整、パンフレットなどの準備を行い、会も盛況に終わりました。あしなが学生募金事務局としての活動はこれが最後になりました。
あしなが育英会、あしなが学生募金、また世の中に存在するたくさんのあしながさんの多大なるご理解ととご協力に、深く御礼を申し上げます。
また3月には、奈良県にあるどろどろ研究所とコラボして、モノづくりのワクワクを伝えるため、ワークショップの開催を行いました。どろどろ研究所は小中学生を中心とする図工教室であり、2024年の夏ごろに後輩が教えてくれ、それ以来稀に顔を出して一緒にものづくりをするようになっていました。今回はそこでワークショップをさせていただくことになりました。
ワークショップは準備がすごく大変で、後輩たちの手も借りながら小中学生が楽しんでもらえるものを目指しました。当日はグダグダになることもありましたが、たくさんの子供たちの笑顔がそこにありました。これが7年前からの私の生きる道なんだなと、改めて気づくことができた本当にいい機会でした。
開催の場を提供くださいました、どろどろ研究所の皆さん、運営協力に手伝ってくださった後輩たち、ご参加くださった皆様に、この場にて深く御礼を申し上げます。

さて、高専での生活やインターンで磨くことができた技術と、あしながやその他数多くの活動で培った様々なスキルを活用し、私はこれからも社会のため変革を目指す人間であり続けます。なので高専でエンジニアを目指す高専生の後輩たちにも、自分の進む道を信じてほしいと思います。
あなたが抱く理不尽は、決して蔑ろに飲み込んではいけません。同じことを思っている人たちはこの世界に幾万と存在しています。変えられるものから変えていきませんか。あなたはほかの高校生や大学生とは違って、世の中を良くする力を持つ技術を、試せる場にいるのですよ。
高専では、今日を生き抜く強さ、明日を変え行く賢さを備え、環境を変えられる者こそ、本当の意味でのエンジニアになれる。まだ数多くの罪を抱きそれと闘いながら生きている未熟な私ですが、その七年の道を進んだ今、本当に強くそう思います。
最後になりましたが、チャレンジプロジェクトにご理解とご協力をいただきました企業の皆様、たくさんの活動をさせてくださいました奈良高専とその関係者の皆様、研究室や電研、柔道部の皆様、また、留年や家事など本当にいつも迷惑と気苦労をかけてしまっていた家族・親族の皆様、このブログを読んでいただいております読者の皆様、
私というちっぽけな人間に携わってくださいましたすべての皆様に、深く感謝を申し上げます。本当に、ありがとうございました。
今後ともこのブログを、よろしくお願い致します。